福祉用具貸与
福祉用具貸与(レンタル)
- 要介護認定等を受けた人(ただし、要支援1・2及び要介護1の認定を受けた方は取り扱いが異なります。)が在宅で車椅子や特殊ベッドなど日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で福祉用具の貸与を受けることができます。
- 介護サービスの計画(ケアプラン)を作るときに、介護支援専門員に相談してください。
対象になる用具の種類
|
用具 |
種類 |
|---|---|
|
車いす |
|
|
車いす付属品 |
クッション・電動補助装置などで、車いすと一体的に使用されるもの |
|
特殊寝台 |
サイドレールが取りつけてあるもの又は取りつけることが可能なものであって、背や脚の傾斜角度が調整できる機能のあるものか、床板の高さが無段階に調節できるもの |
|
特殊寝台付属品 |
(注意)入浴介助用ベルトについては特定福祉用具販売対象品です。 |
|
床ずれ防止用具 |
|
|
体位変換器 |
空気パッド |
|
手すり |
|
|
スロープ |
取り付けに工事を伴わないもの |
|
歩行器 |
|
|
歩行補助杖 |
|
|
認知症老人徘徊感知器 |
認知症の高齢者等が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族や隣人等へ通報するもの |
|
移動用リフト |
取り付けに住宅改修を伴わないもの |
|
自動排泄処理装置 |
次の要件を全て満たすもの
|
【令和6年4月~】
次の福祉用具は、利用方法(借りる又は購入)を選択できます。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉杖は除く)及び多点杖
経費
各用具ごと事業者ごとに1月の利用単価は異なりますので、各事業所もしくはケアマネジャーにお尋ねください。なお、利用者負担はその額の1割(2割、3割)となります。
(注意)利用者負担の割合は「介護保険負担割合証」で確認してください。
軽度者の福祉用具の貸与について
要支援1・2及び要介護1の人については車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません。
ただし、状態像に応じて一定の条件に該当する人については例外的に保険給付の対象となります。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて
1 例外給付の取り扱いについて
要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用を想定しにくいため、原則として介護報酬は算定できませんが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。したがって、軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当者(以下「ケアマネジャー等」とする)が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。
2 例外給付の対象品目
要支援1、要支援2、及び要介護1の方
「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」
「認知症老人俳諧感知器」「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」「自動排泄処理装置(尿のみ自動的に吸引する機能のものを除く。)」
要介護2、要介護3の方
「自動排泄処理装置(尿のみ自動的に吸引する機能のものを除く。)」
3 例外給付の対象となる要件
(1)直近の認定結果により下記表1の状態像が確認できる場合
必要性については、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャーが判断してください。
|
状態像 |
認定調査の結果 |
|---|---|
|
(ア)日常的に歩行が困難な者 |
基本調査1-7 「3、できない」 |
|
(イ)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
(注釈) |
|
状態像 |
認定調査の結果 |
|---|---|
|
(ア)日常的に起きあがりが困難な者 |
基本調査1-4 「3、できない」 |
|
(イ)日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3 「3、できない」 |
|
状態像 |
認定調査の結果 |
|---|---|
|
日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3 「3、できない」 |
|
状態像 |
認定調査の結果 |
|---|---|
|
(ア)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解 のいずれかに支障がある者 |
基本調査3-1 「調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外 |
|
(イ)移動において全介助を必要としない者 |
基本調査2-2 「4、全介助」以外 |
|
状態像 |
認定調査の結果 |
|---|---|
|
(ア)日常的に立ち上がりが困難な者 |
基本調査1-8 「3、できない」 |
|
(イ)移乗が一部介助または全介助を必要とする者 |
基本調査2-1 「3、一部介助」又は「4、全介助」 |
|
(ウ)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
(注釈) |
|
状態像 |
認定調査の結果 |
|---|---|
|
(ア)排便が全介助を必要とする者 |
基本調査2-6 「4、全介助」 |
|
(イ)移乗が全介助を必要とする者 |
基本調査2-1 「4、全介助」 |
(注釈) アの(イ)及びオの(ウ)については、該当する認定調査結果がないため、「主治の医師から得た情報」及び「サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント」によりケアマネジャー等が判断してください。
「主治の医師から得た情報」は書面に限らないが、連携不十分とならないよう留意し、照会・回答内容について必ず記録してください。
- a.「歩行ができる」であっても、日常生活範囲における移動の支障が特に必要と認められる者として、ケアマネジメントにより地域の実情等を含め総合的に判断を行ってください。「長距離歩行は移動ではない」「屋外は日常生活範囲に含まれない」という判断ではありません。
- b.昇降座椅子については、認定調査項目で判断する場合、「立ち上がり」ではなく、「移乗」で判断してください。「立ち上がり」はいすやベット、車いすに座っている状態からの立ち上がりを評価するものです。昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものですから、「畳からポータブルトイレへの乗り移り」を評価する「移乗」の認定調査項目を用いる必要があります。
(2)(1)に該当しない場合でも、下記の状態像に該当することを大崎上島町が書類等確実な方法で確認することができる場合
確認申請手続きの実施方法
- ア 利用者の状態の確認およびアセスメントの実施
ケアマネジャー等は、利用者の状態像の確認及びアセスメントの実施により、当該利用者の状態が次に示した1.から3.の状態像に該当する可能性、及び福祉用具貸与が適当か否かを判断します。- 1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日々によって又は時間帯によって、頻繁に表1の「状態像」に該当する者
- 2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに頻繁に表1の「状態像」に該当するにいたることが確実に見込まれる者
- 3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から表1の「状態像」に該当すると判断できる者
-
イ 医学的所見の確認
ケアマネジャー等は、アセスメントにより福祉用具の貸与が適当と考えた場合、次のいずれかの方法により医師の意見(医学的な所見)を照会し状態像1.から3.のいずれかに該当することを確認します。なお、医師に対して医学的な所見を確認する場合、単に情報提供を求めるのではなく、担当ケアマネジャー等としてのアセスメント内容、及び必要と考えられる福祉用具の種類等、必要な情報を明らかにしてください。- (ア)要介護認定の主治医意見書
-
ケアマネジャー等は利用者の同意を得て主治医意見書の写しを大崎上島町から入手し、状態像1.から3.のいずれかに該当することを確認してください。
-
主治医が主治医意見書作成の際にあわせて記載する場合は「特記すべき事項」欄に、利用者が1.から3.に類型化された状態像に該当する旨を文章で記載してください。
-
- (イ)医師の所見の聴取
-
少なくとも、イ疾病名を含む医学的な所見と、ロ該当する状態(例 寝返りが困難、もしくは医学的に禁止されている等)を具体的に聴取し、その結果1.から3.のどの状態像に該当するかについて、医師の明確な判断を得ることが必要です。
-
ケアマネジャー等は「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る医学的所見について」3点を明記し医師の確認を行ってください。主治医意見書、診断書についても同様に、この3点が明記されている場合に、添付資料とすることができます。
-
- (ア)要介護認定の主治医意見書
(3)サービス担当者会議の開催等、適切なケアマネジメントの実施
ケアマネジャー等は、確認した医学的な所見を踏まえ、サービス担当者会議を開催等、適切なケアマネジメントを実施した結果を、特に福祉用具貸与が必要であると判断した場合、サービス担当者会議の記録とケアプラン(介護予防ケアプラン)にその内容と医療機関名、医師名および医学的な所見を明記し、確認依頼申請書を作成してください。なお、利用者に対し、確認申請手続きを代行すること等について説明を行い、確認依頼申請に同意を得てください。
提出書類
医学的な所見の確認書類(「主治医意見書(写し)」または例外給付に係る医学的所見について
- 医学的な所見の確認書類(「主治医意見書(写し)」または例外給付に係る医学的所見について
- 要介護の場合:居宅サービス計画書(1)・(2)(写し)
サービス担当者会議の要点(写し) - 要支援の場合:介護予防サービス・支援計画書(1)・(2)(写し)
介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)(写し)
4 福祉用具貸与の実施
- ケアマネジャー等はケアプラン(介護予防ケアプラン)を確定し、利用者に説明した上で同意を得て当該ケアプランを交付してください。
- ケアマネジャー等は(介護予防)福祉用具貸与事業所にケアプラン(介護予防ケアプラン)を交付するとともに、利用者の同意を得て、大崎上島町から通知された保険給付開始日、福祉用具の種類等、貸与に必要な情報を提供します。
- (介護予防)福祉用具貸与事業所等は利用者の状態像に適した福祉用具を保険給付対象として貸与します。
5 必要性の検証
- 福祉用具貸与実施後は、ケアマネジャー等がモニタリング(少なくとも月1回)・介護予防ケアプランの評価(必要に応じて随時)等の手段によって、必ずその必要性を見直し、その結果を記録します。
- ケアマネジメントの結果、不要となれば「貸与中止」とします。
- 「種目変更」「貸与再開」が必要となれば、再度「確認依頼申請」手続きを行います。
事後に行われた大崎上島町の実施調査及び監査等によって、見直しが適切に行われていなかったことが判明した場合は保険給付の返還対象となります。
あくまでも軽度者への貸与は原則保険給付対象外であることを踏まえ、適切なケアマネジメントのもとで運用を行ってください。
当該被保険者が更新認定・要支要介申請・区分変更を受けたときは再度提出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課 保険係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
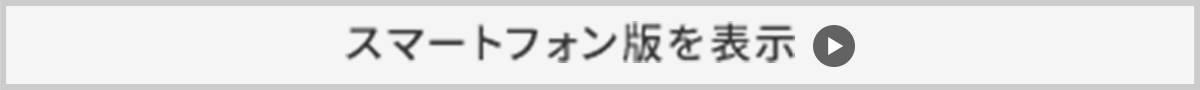








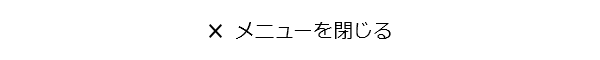

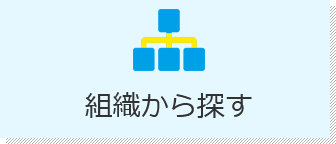
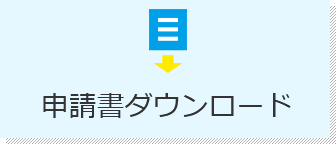




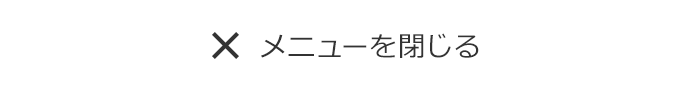
更新日:2025年11月28日