国民健康保険税の軽減制度
所得が少ない方への国民健康保険税の軽減
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の総所得金額が一定金額以下の場合、その世帯の均等割額と平等割額をそれぞれ軽減します。
軽減の割合
世帯主とその世帯の国保加入者の前年の総所得金額等が、次の基準以下である場合、均等割額と平等割額をそれぞれ軽減します。
7割軽減の所得基準
43万円+10万円×(給与所得者等数-1)
5割軽減の所得基準
43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(30万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)
2割軽減の所得基準
43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(56万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数)
• 給与所得者等数とは、給与収入が55万円を超えている方や年金収入が60万円(65歳以上の方は110万円)を超えている公的年金受給者の方、またはその両方を満たす方のことをいいます。
※65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
• 同一世帯の中に所得が分からない方(未申告の方)がいる場合、世帯所得の判定ができないため、軽減することができません。未申告の方には「国民健康保険税に関する所得申告書」を送付する場合がありますので、必ず提出してください。
• 国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している方、またその同一世帯の方は、所得の有無に関係なく、毎年必ず所得の申告を済ませましょう。
未就学児に係る保険料均等割額の軽減
令和4年度以降の国民健康保険税について、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国保に加入している未就学児の均等割額(介護保険分の均等割は除く)を5割減額します。
なお、低所得世帯への法定軽減(7・5・2割軽減)に該当する世帯については、法定軽減後、さらに未就学児に軽減が適用されます。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割の軽減となります。
未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
75歳になる方や一定の障がいにより広域連合の認定を受けた65歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同一世帯の他の被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
この場合、国民健康保険税の基礎課税額と後期高齢者支援金課税額に係る平等割額が半額(「7割軽減」、「5割軽減」、「2割軽減」の場合は軽減後の額が半額)になります。
なお、6年目からの世帯を「特定継続世帯」といい、平等割額は4分の1減額となります。
特定世帯または特定継続世帯であるかどうかは、賦課期日時点で判断します。ただし、世帯主が変わった場合は適用対象外となり、その月以降の平等割は軽減されません。(国民健康保険加入者が2人以上になったり、世帯主に異動がないまま世帯所属者の異動があった場合は、次の賦課期日まで軽減が続きます。)
旧被扶養者該当による所得割の減免と均等割の軽減
75歳になる方が、会社の被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳までの方)が新たに国民健康保険に加入する場合は、所得割が当面の間免除され、均等割が資格取得から2年間 2分の1に軽減されます。また、旧被扶養者のみで構成される世帯の場合、平等割も資格取得から2年間 2分の1に軽減されます。
※ この軽減を受けるためには、「国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者)」の提出が必要です。
旧被扶養者とは、次の要件をすべて満たす方のことです。
・ 国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である方
・ 国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険(国保組合等の一部保険を除く)の
被扶養者であった方
・ 国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その
翌日に後期高齢者医療制度の被保険者に該当する場合
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方(非自発的失業者)の軽減
倒産、解雇、雇い止めなどにより本人が自ら望まないかたちで離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定を行い、給与所得に係る所得割を軽減します。
この軽減を受けるためには「国民健康保険税軽減申告書(特例被保険者用)」の提出が必要です。本庁税務課窓口までお越しください。
対象者
・雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などにより離職した方)
・雇用保険の特定理由資格者(雇い止めなどにより離職した方)
・失業時点で65歳未満の方
・平成21年3月31日以降に離職した方
雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由資格者」とは、公共職業安定所(ハローワーク)で交付された、雇用保険受給資格者証の離職理由欄コードが次のいずれかに該当する方です。
倒産・解雇などによる離職「雇用保険の特定受給資格者」:11、12、21、22、31、32
雇い止めなどで離職した「雇用保険の特定理由離職者」:23、33、34
高齢受給資格者(65歳以上の方)及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減対象期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
届出に必要なもの
・雇用保険受給資格者証(※紛失の場合は、ハローワークで再発行が必要です)
・印鑑
・国民健康保険証
産前産後期間における保険税の軽減
令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まります。国民健康保険加入者(被保険者)で妊娠85日以降に出産した方は、出産予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月(出産月)という。」)の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月(出産月)の3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額の全額が軽減されます。
対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85 日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除方法
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。
| 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | |
| 単胎の方 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 多胎の方 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
★…軽減対象月
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
産前産後保険税軽減リーフレット(PDFファイル:438.9KB)
届出に必要な書類
1.保険税軽減届出書(PDFファイル:92.8KB)
2.母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です
3.来庁者の本人確認書類
その他の減免
その他、災害による被害を受けた等の理由で納税が困難なときも減免を受けられる場合があります(所有資産の状況や生活状況などを含め総合的に判断します)。
減免を受けようとする時は、税務課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 税務課
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
電話:0846-65-3114 ファクシミリ:0846-65-3198
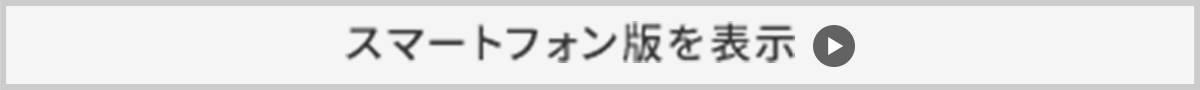








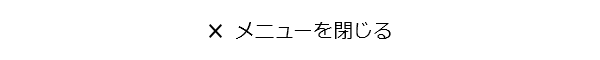

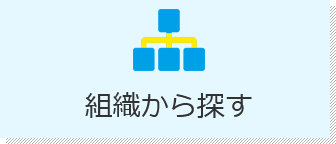
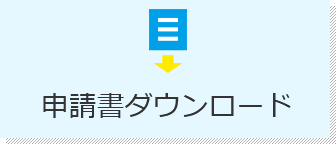




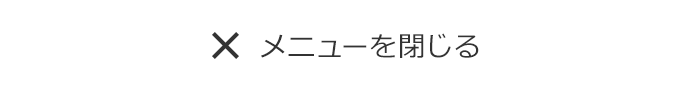
更新日:2025年04月01日