こども医療費助成
大崎上島町に住んでいる0歳から高等学校卒業までのこどもが、医療機関で保険診療を受ける際の自己負担分を助成します。
助成対象者
1.大崎上島町に住所を有している高校生以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)のこども
2.通学等の理由で町外に住所を有するこどもであっても、住所地においてこども医療費の給付がない場合は対象者となります。(ただし、保護者の住所地は大崎上島町に限ります。)
所得制限
所得制限はありません。
一部負担金(自己負担額)
| 対象年齢 |
医療費負担額 (支払限度日数) |
その他 |
|
0歳から 高校3年生 |
1日最大500円 (入院は月14日まで、 通院は月4日まで) |
保険診療にかかる医療費の 2割または3割が500円に 満たないときはその額が 支払額です。 |
※保険薬局での調剤、治療用補装具に関する一部負担金はありません。(一部例外有り)
※入院時の食事負担金及び健康診断、予防接種、歯科矯正等保険給付の行われないものについては、対象になりません。
申請手続き
お子さんが出生した場合や他市町から転入した場合は、申請手続きが必要です。
必ず異動日(出生日や転入日)から14日以内に手続きをしてください。遅れると、資格発生日からの認定が出来ない場合があります。
※原則、申請日から資格有効となります。
申請に必要なもの
1.保護者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
2.対象となるこどもの健康保険の資格情報が分かるもの
(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの保健情報確認画面のスクリーンショット、健康保険証等)
※保険加入手続き中等でこどもの健康保険証が出来ていない場合は、提出は後日でかまいません。
申請窓口
健康福祉課(木江支所)、本庁住民課、大崎支所窓口係
受給者証の使い方

🍋受給者証は広島県内で有効です🍋
・町が交付する「こども医療費受給者証」と健康保険証を、県内の医療機関等の窓口に提示すれば、一部負担金のみで診療が受けられます。
・なお、県外での受診については、償還払いとなりますので、医療機関等の窓口で自己負担金相当額を支払っていただき、後日、領収書を添えて健康福祉課へ申請してください。
・受給対象のこどもが通園または通学している幼稚園・学校等の管理下でのけが等で治療を受けた場合は、日本スポーツ振興センターから災害共済給付があるので、使用しないでください。
再交付の手続き
紛失された場合等はこども医療費受給者証の再交付を健康福祉課(木江支所)、本庁住民課、大崎支所窓口係で申請してください。
資格の喪失
転出等でこども医療費の対象でなくなる場合は、こども医療費受給者証を役場窓口に返還してください。
償還払いの手続き
広島県外の医療機関を受診した場合や、医療機関でこども医療費受給者証を提示出来なかった等の理由で、自己負担額を超える医療費を支払った場合は、申請により支払った医療費から自己負担分を除いた額を給付します。
〇手続きは、窓口での手続き、もしくは郵送にて対応しています。
※高額医療費の対象となる時や、保険証を提示せず医療費を全額(10割)負担された時は、先に加入している健康保険組合等への手続きが必要です。
申請に必要なもの
・こども医療費受給者証
・領収書(保険点数の記載があるもの)・保険薬局の領収書の写し
・還付先の口座登録(受給者証に記載された保護者名義)
各種様式
(こども医療費)記載事項変更届(RTFファイル:70.9KB)
(こども医療費)再交付申請書(RTFファイル:57.4KB)
(こども医療費)償還払申請書(Wordファイル:19.5KB)
【記入例】こども医療費償還払い(PDFファイル:247.4KB)
上手な医療機関へのかかり方
〇 「かかりつけ医」を持ちましょう
「かかりつけ医」とは、身近で頼りになり、日ごろから医療や保健などの相談ができる上、必要なときには専門医や専門医療機関を紹介できるお医者さんのことです。
本人や家族の病状や病歴、家族構成、薬などのアレルギーの有無などを把握しているので、もしもの時に素早い診療ができます。
〇 ジェネリック医薬品を使ってみましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められているお薬です。
ジェネリック医薬品は開発費が少ないため、新薬より低価格となります。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。
〇 同じ病気で複数の医療機関を受診することはやめましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費の負担が増えるだけでなく、重複する検査や投薬により、体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。
信頼できる「かかりつけ医」に相談や助言を受けましょう。
〇 コンビニ受診はやめましょう
コンビニ受診とは、夜間や休日など一般診療時間外に軽症患者などが救急外来を受診することと言われています。
コンビニ受診が増えることで、救急外来が混み合い命にかかわるような重症患者への対応が遅れてしまったり、病院のスタッフが疲弊することから、地域の救急医療体制が維持できなくなる恐れがあります。
〇 休日・夜間は電話相談を活用しましょう
休日・夜間に、医療機関を受診するかどうか迷ったり、体調不良やケガへの対処等について相談したい時には、#7119や#8000の電話相談を活用しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課 福祉係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304
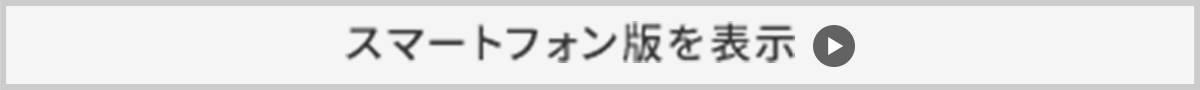








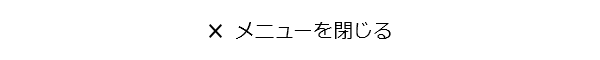

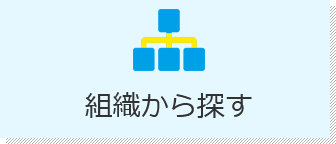
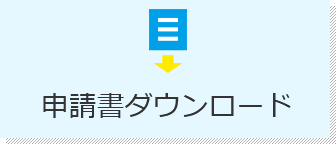




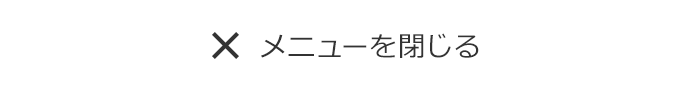
更新日:2023年10月01日